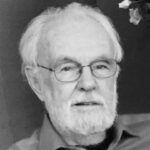はじめに
1980~90年代、イギリスやアメリカでは地理教育の大規模な改革が行われました。「何を教えるべきか」「知識重視かスキル重視か」「標準化と地域性の両立」など、地理教育の根幹に関わる議論が活発に展開されたのです。
この改革により、イギリスでは「National Curriculum for Geography」、アメリカでは「Geography for Life(National Geography Standards)」が制定され、地理教育の知識体系や目標が明文化されました。しかし、この標準化には光と影の両面があることが次第に明らかになってきました。
標準化カリキュラムの意義と課題
標準化の意義
標準化カリキュラムは、すべての学校や教師が教える内容や達成すべき学習目標を国や州レベルで細かく規定する仕組みです。その最大の意義は、公平性と教育の質保証にあります。すべての学校・生徒に等しく重要な知識を届けることで、教育格差の解消を目指していたわけです。
しかし、問題も浮上した
一方で、標準化が進むことで新たな課題も生まれました。特に深刻なのは、教員の専門性と創造性が制限されてしまう場合があったこと、そして深い学問的知識(PDK: Powerful Disciplinary Knowledge)が軽視されてしまうことでした。
教員の裁量と専門性への制約
定められたカリキュラムの範囲内でしか授業が許されないため、教員が地域の特性や生徒の興味に応じて教材やテーマを自由に選択・設計することが困難になりました。これにより、現場教員が「カリキュラムメーカー」としての創造的役割や専門的判断力を発揮しにくくなるという問題が浮上することになりました。
深い学問的知識(PDK)の軽視
標準カリキュラムでは、汎用的・基礎的な知識や技能を重視する傾向があり、専門的で抽象度の高い学問知識を十分に組み込めないという課題があります。
具体的には以下のような問題が生じています:
- 地理学に固有の高度な空間概念の軽視
- 批判的思考の枠組みの不足
- 学問的な探究過程の軽視
- 「テスト可能で標準化しやすい知識」への偏重
これらの結果、教室での学びが詰め込み型・暗記中心になりやすく、地理的な探究的学習や現場の多様なニーズを反映したカリキュラム展開が困難になる場合が出てきました。
なぜこれが問題なのか
地理教育における「Powerful Disciplinary Knowledge(PDK)」は、単なる事実の知識を超えて、学問的に裏付けられた論理的思考や社会批判の視点などを含む高度な知識体系です。
これが育たないと、生徒は「ただ知っている」だけで終わり、地理学的な思考力や判断力が育ちにくくなります。また、教員が専門性や地域の実情を踏まえてカリキュラムを設計する能力が活かせなければ、生徒の多様な背景や興味に応じた教育の実現が困難となります。
ジオ・ケイパビリティの登場
これらの課題が表面化する中、ヨーロッパを中心にして「ジオ・ケイパビリティ(GeoCapabilities)」という新たな枠組みが提唱されました。
GeoCapabilitiesプロジェクトは2012年にアメリカ地理学会(AAG)主導の予備調査から始まり、2013年にはEU資金によるComeniusプロジェクトとして正式に開始されました。これは、教師がカリキュラムメーカーとして地域や生徒に即した教材設計を行い、深い学問知識を活かして「生きる力」を育むためのアプローチです。
GeoCapabilitiesの特徴は、セン(Amartya Sen)やヌスバウム(Martha Nussbaum)のCapability Approachを基盤としているところです。また、PDK(Powerful Disciplinary Knowledge:強力な学問的知識)を中軸に据えつつ、社会正義や価値観、多様な視座を取り込む拡張が図られています。
おわりに
地理教育の標準化は、教育の公平性を保障する重要な役割を果たしました。しかし同時に、教員の専門性や創造性、そして深い学問的知識の軽視という課題も生み出しました。
GeoCapabilitiesプロジェクトは2021年に正式には終了しましたが、その理念とアプローチは世界各地のパートナーによって継続的に発展させられています。標準化の課題を乗り越え、より豊かで多様性に富んだ地理教育の実現を目指したこの取り組みは、今後の地理教育に重要な示唆を与え続けて行くことになるでしょう。