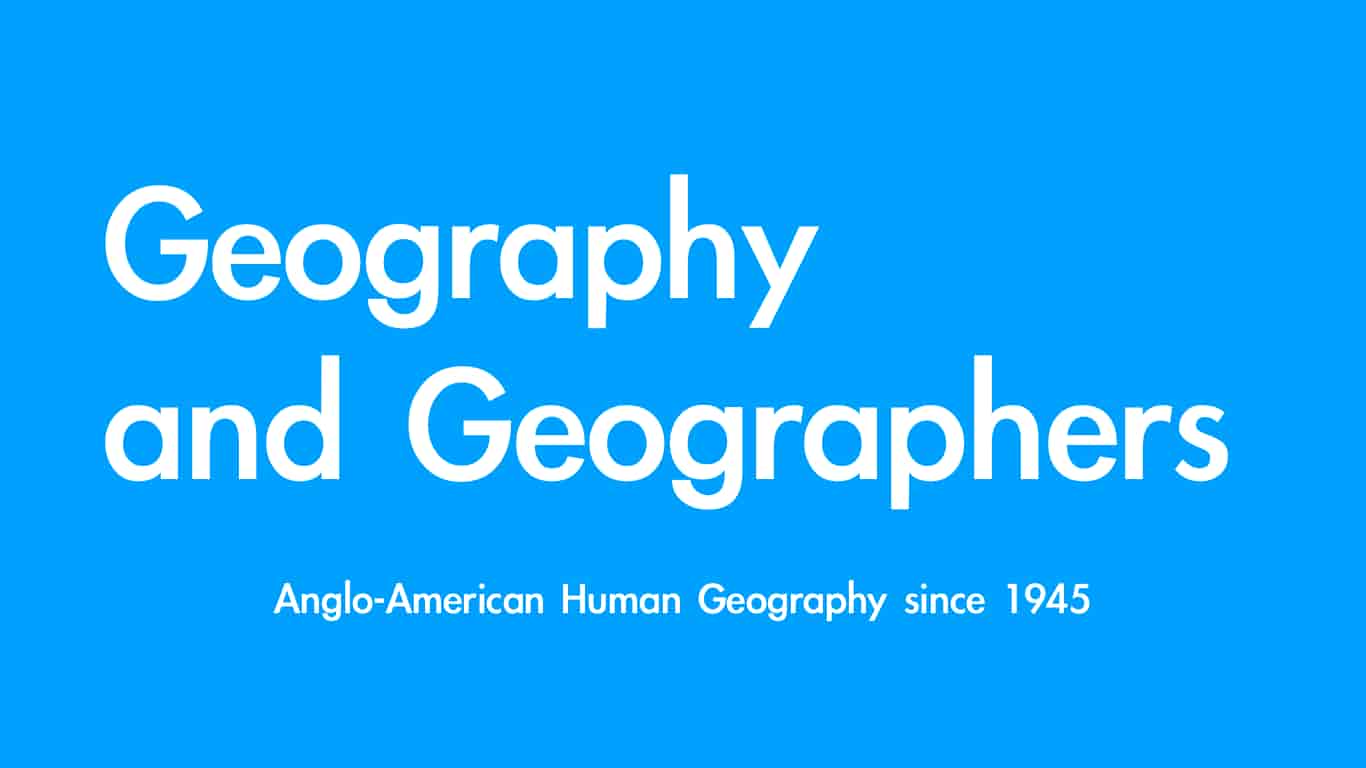人文地理学の歩みを理解するために、Ron Johnstonの『Geography and Geographers: Anglo-American Human Geography since 1945』は必読です。どの版を読んだ(読まされた)か覚えていますか?第7版以降は改訂版が出ていないので、この質問ができる方々は限定されてしまうのかもしれません・・・
この記事では、Ron Johnston & James Sidawayの『Geography and Geographers: Anglo-American Human Geography since 1945』(第7版, 2015年)の章立てを参考にしながら、戦後英語圏人文地理学の理論的変遷と主要学者の貢献について概説します。
前にも、同じような記事を書いていますが・・・
戦後初期:地域地理学の黄金時代と危機(1945年-1950年代前半)
戦後初期の英語圏人文地理学は、戦前から継承された地域地理学(Regional Geography)が支配的でした。Richard Hartshorneの『The Nature of Geography』(1939年)の影響下で、地理学は「地表の地域的差異の記述と説明」を目的とする学問として位置づけられ、記述的・個性記述的なアプローチが主流でした。
しかし、1950年代に入ると、ハーバード大学地理学科の廃止(1948年)に象徴される地理学の「学術的危機」が顕在化し、既存の地域地理学に対する批判が高まりました。特にFred Schaeferの論文(1953年)は、地理学の科学化を強く主張し、後の理論的転換の契機となったのです。
計量革命:空間科学としての再構築(1950年代後半-1960年代)
理論的背景と展開
1950年代後半から1960年代にかけて、英語圏人文地理学は計量革命(Quantitative Revolution)を経験しました。この転換は、地理学を記述的学問から空間科学(Spatial Science)として再構築しようとする試みでした。
主要な理論的支柱は以下の通りです:
- 空間の数学的概念化:ユークリッド幾何学に基づく絶対空間概念の採用
- 実証主義的方法論:統計学・数理的手法による法則定立的(nomothetic)アプローチ
- 立地理論の発展:Walter ChristallerやAugust Löschの中心地理論、Walter Isardの地域科学の影響
革命を牽引した学者たち
この時期の代表的な学者たちとその貢献を見てみましょう:
- William Garrison(ワシントン大学):交通地理学における数理モデルの開発
- Peter Haggett(ケンブリッジ大学、後にブリストル大学):『Locational Analysis in Human Geography』(1965年)で立地分析の体系化
- Richard Chorley(ケンブリッジ大学):理論地理学と地理学方法論の体系化
この時期の地理学は、空間パターンの規則性と予測可能性を重視し、人間の経済活動や居住パターンを数理モデルで説明しようと試みました。
人間主義地理学の反撃:数字では測れない人間の営み(1960年代後半-1970年代)
空間科学への批判と新たな視座
1960年代後半から、空間科学の機械論的・還元主義的アプローチに対する批判が高まりました。この文脈で登場したのが人文主義[人間主義]地理学(Humanistic Geography)と行動地理学(Behavioral Geography)です。
人文主義[人間主義]地理学の主要な特徴:
- 現象学的アプローチ:人間の意識と経験を重視
- 場所の意味論:Yi-Fu Tuanの「トポフィリア」概念とEdward Relphの「場所性」理論
- 主観的空間の研究:mental mapやcognitive mappingの導入
行動地理学の展開:
- Herbert Simonの「satisficing behavior(限定合理性)」概念の地理学的応用
- 空間認知と意思決定プロセスの解明
- 環境心理学との学際的連携
ラディカル地理学:社会正義を求めた地理学者たち(1970年代-1980年代前半)
革命への転換
1970年代に入ると、ラディカル地理学(Radical Geography)が台頭しました。この潮流は、地理学を社会変革の手段として位置づけ、資本主義的空間関係の批判的分析を展開しました。
主要な理論的貢献:
- David Harveyの理論的転換:
- 『Social Justice and the City』(1973年):都市問題のマルクス主義的分析
- 『The Limits to Capital』(1982年):資本の空間的循環理論
- Neil Smithの「不均等発展論」:資本主義における地理的不平等の構造的説明
- Doreen Masseyの「空間分業論」:産業立地と地域発展の政治経済学的分析
制度的発展:
- 雑誌『Antipode』(1969年創刊)の影響力拡大
- 「Union of Socialist Geographers」の結成
ポストモダンの嵐:多様性の時代へ(1980年代後半-1990年代)
文化論的転回と新たなパラダイム
1980年代後半から1990年代にかけて、人文地理学はポストモダン的転回を経験しました。この時期の特徴は理論的多様性の急激な拡大です。
ポスト構造主義地理学の展開:
- Jacques DerridaやMichel Foucaultの哲学の導入
- 表象の危機への注目と権力関係の言説分析
- 「脱構築」手法の地理学的応用
「空間論的転回(Spatial Turn)」の影響:
- Edward Sojaの「第三空間」概念
- 空間と社会の弁証法的関係の再理論化
文化地理学の再活性化:
- 「新文化地理学」の登場とカルチュラル・スタディーズとの連携
- 景観の記号論的・イデオロギー的分析
ジェンダー地理学:女性の視点が変えた地理学(1970年代後半-現在)
フェミニスト視点の制度化
フェミニスト地理学は1970年代後半から本格的に発展し、地理学における男性中心的バイアスを批判しました。
発展段階:
- 「女性の地理学」段階(1970年代後半-1980年代前半):
- 空間的制約とジェンダー不平等の関係分析
- Women and Geography Study Groupの『Geography and Gender』(1984年)
- ジェンダー関係の地理学(1980年代後半-1990年代):
- Linda McDowellやDoreen Masseyの理論的貢献
- 公私空間の二分法批判
- インターセクショナルなアプローチ(1990年代以降):
- 人種・階級・セクシュアリティとの交差分析
- ポストコロニアル・フェミニズムの導入
現代地理学:統合と新たな挑戦(1990年代以降)
理論的統合と新たな課題
1990年代以降の人文地理学は、前述の諸潮流の選択的統合と新たな理論的課題への対応が特徴的です:
- 関係論的地理学:アクターネットワーク理論やアセンブリッジ理論の導入
- 非表象理論:Nigel Thriftらによる身体性と情動の地理学
- ポストコロニアル地理学:西洋中心主義的知識体系への批判
- 環境地理学の新展開:政治生態学とアントロポセン論(人新世論)の影響
おわりに:地理学の未来を考える
戦後英語圏人文地理学の発展史は、科学性への志向と人文学的探求の弁証法的関係として理解できます。空間科学から人間主義地理学、ラディカル地理学からポストモダン地理学への展開は、地理学という学問の認識論的・方法論的多様性の拡大過程を示しています。
Johnston & Sidawayが第7版で強調するように、現代の人文地理学は「変化する学問分野」として、学際性と理論的開放性を特徴としています。この歴史的展開は、地理学が単なる空間記述を超えて、社会・文化・政治・環境の複合的理解を志向する総合的人文社会科学として成熟していく過程として評価されます。
地理学の理論的発展を振り返ることで、現代社会の空間的問題に対する多角的なアプローチの重要性がより明確に理解できるでしょう。今後も地理学は、グローバル化、都市化、環境問題、デジタル化といった現代的課題に対応しながら、さらなる理論的発展を遂げていくことが期待されます。
補足:
『Geography and Geographers: Anglo-American Human Geography since 1945』の出版年と著者
| 版数 | 出版年 | 著者 |
|---|---|---|
| 第1版 | 1979年 | Ron Johnston |
| 第2版 | 1981年 | Ron Johnston |
| 第3版 | 1986年 | Ron Johnston |
| 第4版 | 1991年 | Ron Johnston |
| 第5版 | 1997年 | Ron Johnston |
| 第6版 | 2000年 | Ron Johnston |
| 第7版 | 2015年 | Ron Johnston & James Sidaway |